- 腎臓病
- (更新日:2025年09月18日)
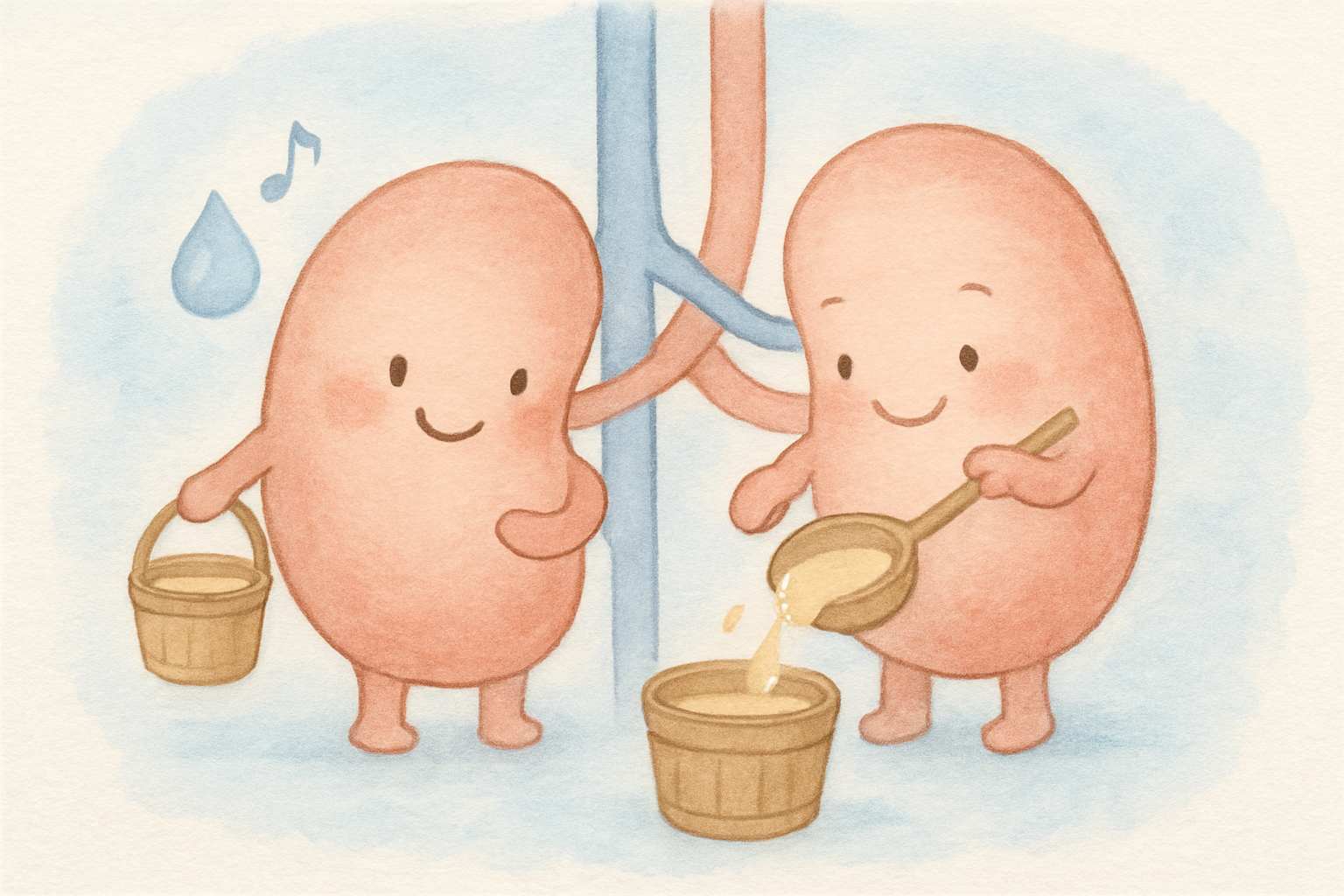
慢性腎臓病とは?|腎臓病の種類と特徴 主な分類と最新治療法
1. 腎臓病とは - 腎臓の働きと重要性
腎臓病とは、さまざまな原因によって腎臓の働きが低下する疾患群の総称です。人間の体には左右に一対の腎臓があり、それぞれが数百万個のネフロンと呼ばれる機能単位から構成されています。腎臓病を理解するには、まずその基本的な機能を知ることが大切です。
1-1. 腎臓の基本的な機能
腎臓には主に以下の重要な機能があります:
老廃物の排泄: 体内で生じた不要な物質や有害物質を尿として体外に排出します
体液量の調節: 体内の水分量を適切に保ち、血圧の維持に貢献します
電解質バランスの維持: ナトリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質濃度を調整します
ホルモン分泌: 赤血球の産生を促すエリスロポエチンや、骨の形成に関わるビタミンD活性化などを行います
酸塩基平衡の調整: 体内のpHバランスを適正範囲に保ちます
これらの機能が障害されると、全身にさまざまな症状が現れるようになります。
1-2. 腎臓病が体に与える影響
腎臓病が進行すると、次のような影響が体に現れます:
むくみ(浮腫): 体液の貯留により、特に足首や顔にむくみが生じます
高血圧: 体液量の増加や腎臓からの昇圧物質の分泌により血圧が上昇します
貧血: エリスロポエチンの産生低下により、赤血球の生成が減少します
骨代謝異常: カルシウムやリンの代謝異常により、骨が脆くなることがあります
心血管疾患のリスク上昇: 腎臓病があると心臓病や脳卒中のリスクが高まります
倦怠感や食欲不振: 老廃物が体内に蓄積することで、全身の不調が生じます
1-3. 腎臓病の早期発見の重要性
腎臓病は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれ、初期段階ではほとんど症状が現れないことが特徴です。腎機能が70%以上残っている段階では、自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断での尿検査や血液検査が重要になります。
早期発見のポイント:
尿検査での蛋白尿や血尿のチェック
血液検査でのクレアチニン値やeGFR(推算糸球体ろ過量)の確認
高血圧や糖尿病など、腎臓病のリスク因子がある人の定期検診
早期に発見できれば、生活習慣の改善や適切な治療により、腎機能の低下を抑えたり、場合によっては改善させたりすることも可能です。
2. 腎臓病の基本分類
腎臓病は、発症の原因や経過などによって様々な方法で分類されます。基本的な分類方法を理解することで、腎臓病の全体像をより明確に把握することができます。
2-1. 原発性腎臓病と続発性腎臓病の違い
腎臓病は原因によって大きく2つに分けられます:
この分類は治療方針を決める上で重要であり、続発性の場合は原因となる疾患の治療も同時に行う必要があります。
2-2. 急性腎臓病と慢性腎臓病の経過による分類
腎臓病は発症から経過の時間や進行の速さによって、急性と慢性に分けられます:
慢性腎臓病は日本では成人の約8人に1人が罹患していると推定され、社会的にも重要な疾患とされています。
2-3. 病変部位による分類(糸球体、尿細管、間質、血管)
腎臓のどの部位に病変が生じるかによっても分類されます:
腎臓病は複数の部位に病変が及ぶことも多く、総合的な評価が重要です。
2-4. 慢性腎臓病(CKD)と急性腎障害(AKI)の患者数と有病率
| 項目 | 慢性腎臓病(CKD) | 急性腎障害(AKI) |
|---|---|---|
推計患者数 | 約1,480万人(2023年推計) | 正確な総数は不明 |
有病率 | 成人の約7〜8人に1人 | 入院患者全体の約23.2% |
年齢層別有病率 | 65〜74歳:約11.8% 75歳以上:約33.3%(3人に1人) | 成人入院患者:21.6%(5人に1人) 小児入院患者:33.7%(3人に1人) |
診断・治療中の患者数 | 62万9,000人(2020年患者調査) | データなし |
透析患者数 | 34万7,474人(2022年末時点) | 一時的透析を要する患者は全AKI患者の約2.3% |
リスク因子 | 高血圧、糖尿病、肥満、加齢、喫煙など | 既存のCKD、加齢、蛋白尿、敗血症、心臓手術など |
発症場所 | - | 院内発症:約42% 院外発症:約58% |
重症度分布 | G1-G2(軽度):約60% G3(中等度):約35% G4-G5(重度):約5% | RIFLE-Risk(軽度):11.5% RIFLE-Injury(中等度):4.8% RIFLE-Failure(重度):4.0% 透析要:2.3% |
主な原因疾患 | 糖尿病性腎臓病(透析患者の39.5%) 慢性糸球体腎炎(約25%) 腎硬化症(約10%) | 虚血、腎毒性物質、敗血症(院内発症) 脱水、感染症(院外発症) |
年間医療費 | 糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患及び腎不全: 1兆5,346億円(2014年度) | データなし |
引用:慢性腎臓病と急性腎障害の日本における患者数の割合について
3. 慢性腎臓病(CKD)のステージ分類
慢性腎臓病(CKD)は、その重症度によって細かく分類されます。この分類は治療方針の決定や予後予測に重要な役割を果たします。
3-1. GFRとeGFRによる腎機能評価
腎機能評価の指標として最も重要なのが、糸球体濾過量(GFR)です:
eGFRの値が低いほど、腎機能が低下していることを示します。
3-2. CKDのステージ1〜5と各ステージの特徴
CKDは腎機能(eGFR)に基づいて、以下の5つのステージに分類されます:
ステージが進むほど、合併症のリスクが高まり、より厳格な治療や管理が必要になります。
3-3. アルブミン尿による重症度分類
CKDの重症度は、eGFRだけでなくアルブミン尿(または蛋白尿)の程度も考慮して評価します:
この重症度分類を用いることで、個々の患者の状態に応じた適切な治療方針を立てることができます。
血液透析関連記事

血液透析 時間 | 血液透析の時間、週3回・4時間が基本の理由は?
「なぜ、透析はこんなに時間がかかるのだろう?」「週に3回、4時間も通院するのは大変だ…」。血液透析を受けているご本人や、そのご家族がこのような疑問や負担を感じるのは、ごく自然なことです。血液透析は、失われた腎臓の機能を代替する命綱であると同時に、生活に大きな制約をもたらす治療でもあります。特に「時間」というテーマは、仕事、家庭生活、そして心身のコンディションに直結する、切実な問題です。
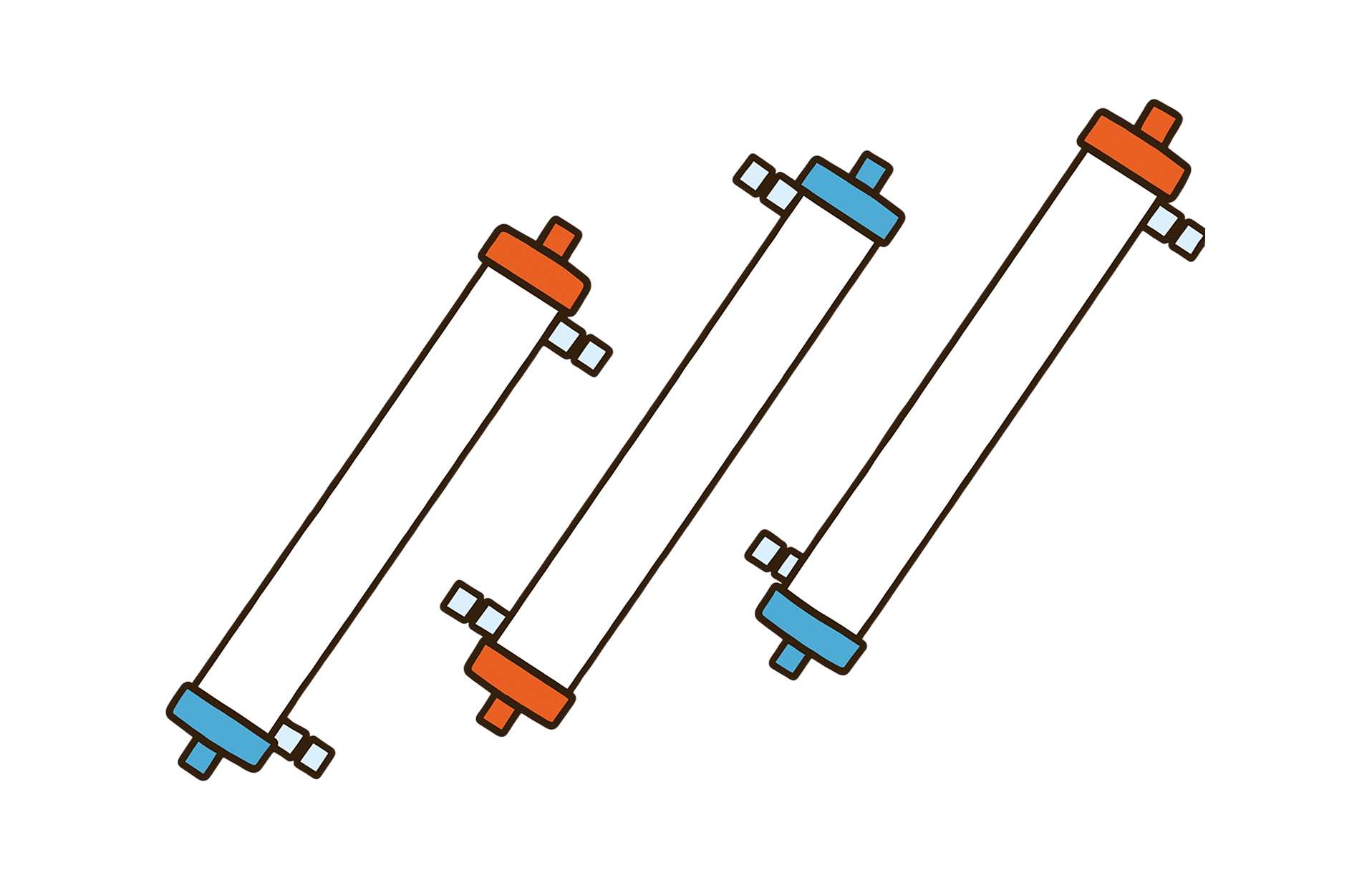
なぜ血液透析が必要になるのか?原因と開始の基準
血液透析は、腎機能がある一定のレベル以下に低下し、薬物療法や食事療法だけでは生命の維持が困難になった場合に選択される治療法です。 どのような状態になると透析が必要になるのか、その医学的な背景と客観的な基準を知ることは、ご自身の状況を正しく理解し、医師からの説明を受け入れるための重要な土台となります。

【合併症について】血液透析
血液透析は、腎機能低下に対する生命維持治療として欠かせない一方、長期治療に伴い多彩な合併症のリスクをはらんでいます。 本記事は、不均衡症候群や高血圧、低血圧、貧血、感染症など、血液透析治療中に起こり得る各種合併症について、原因や症状、具体的な予防・対策方法を体系的に解説します。 医療現場での実践例を踏まえ、早期発見と適切な管理の重要性を深掘りし、安全な治療環境の実現に向けた情報を提供する内容です。
血液透析患者 食事・仕事

透析患者が食べてはいけないもの一覧表 | 食事管理のポイント・食事療法について具体的に解説
透析治療を受けている方々にとって、日々の食事は治療の一環として非常に重要な意味を持ちます。 腎臓の機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなる透析患者さんにとって、食事内容の管理は体調維持や合併症予防に直結するからです。 しかし、「透析 食べてはいけないもの 一覧表」というキーワードで検索されているように、具体的にどのような食品を避け、どのような食事を心がけるべきか、多くの患者さんやそのご家族が悩みを抱えていらっしゃいます。

腎臓病 ミネラル | 透析患者の食事管理・食事療法腎臓病
なぜ飲み物のミネラルが重要なの? 腎臓は体内の余分なミネラル(カリウムやリン)を尿として排出する重要な臓器です。腎臓の働きが弱くなると、これらのミネラルが体内に蓄積し、心臓や骨に悪影響を与える可能性があります。

腎臓に良い食べ物・悪い食べ物|食事療法の基本と実践レシピ
「健康診断の結果、腎機能の低下を指摘された」「家族の腎臓のことが心配で、食事で何かできることはないだろうか」「腎臓に良い食事と言われても、具体的に何から手をつけて良いかわからない」——。このような不安や疑問を抱えている方は、決して少なくありません。

【透析患者の日常生活について】血液透析
血液透析を受ける人の日常生活では、食事や運動、睡眠、シャントの保護など、気をつけるポイントが多岐にわたるといえます。 本記事は、透析にまつわる負担を軽減し、快適な生活を続けるための具体的な工夫や注意点を幅広く紹介します。
血液透析患者の負担を軽減する公的支援制度
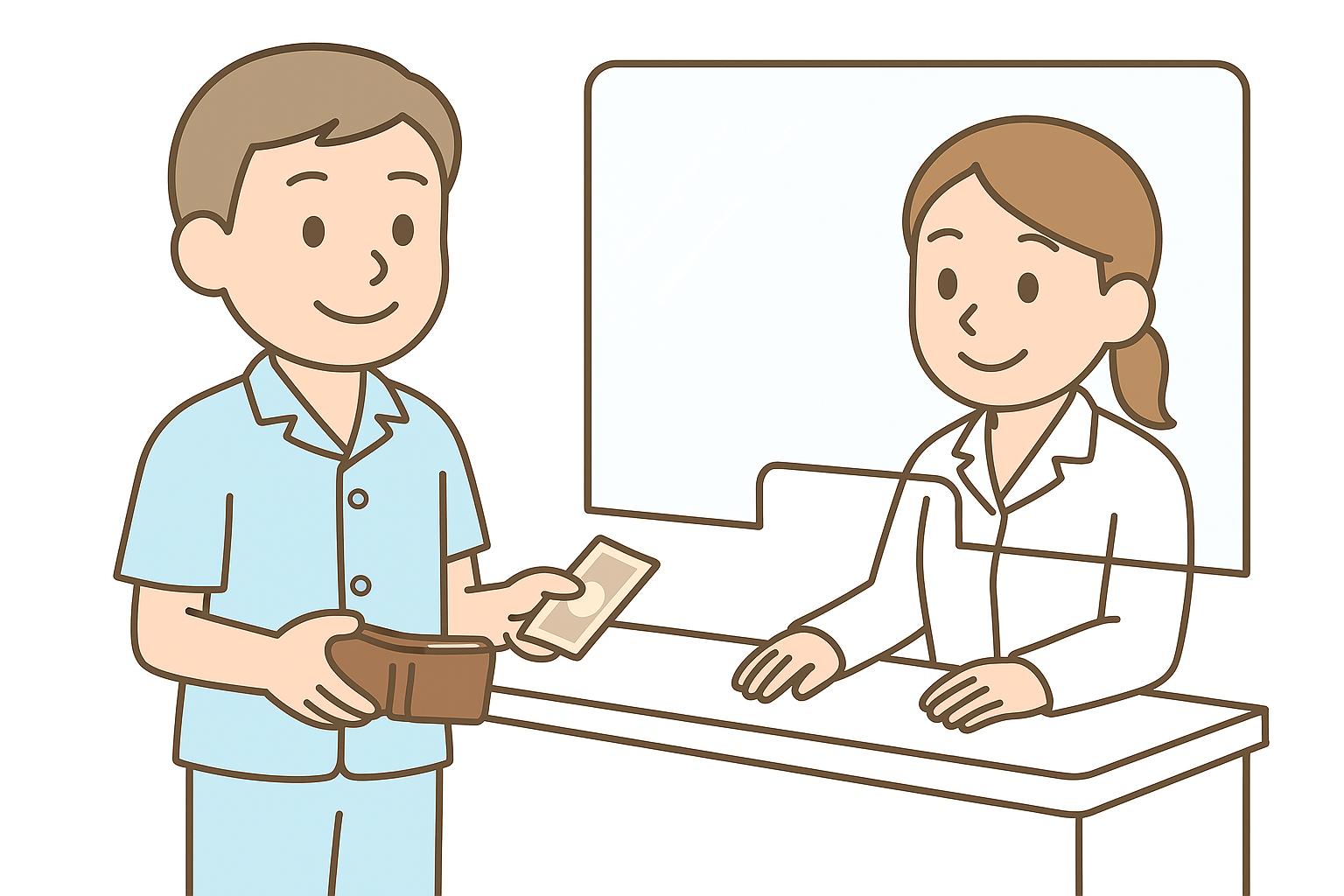
人工透析の費用は?公的制度で自己負担を1万円に抑える方法
「これから人工透析を始めるけれど、費用は一体いくらかかるのだろうか」「生涯にわたる治療費を、本当に払い続けられるだろうか」——。医師から透析治療の必要性を告げられたとき、多くの患者様やそのご家族が、治療そのものへの不安と同時に、重くのしかかる経済的な心配を抱えることになります。 インターネットで検索すると「透析費用は月額40万円」「年間500万円以上」といった数字が目に入り、その金額の大きさに愕然としてしまうかもしれません。しかし、結論から言えば、適切な手続きを踏むことで、その負担を劇的に軽減することが可能です。

【社会保障と福祉制度ガイド】腎臓病で利用できる社会保障と福祉制度
本記事では、腎臓病で治療や生活に影響が出ている方が利用できる各種社会保障や福祉制度について、わかりやすく解説します。 医療費助成、身体障害者認定、介護保険、障害年金、就労支援など、制度ごとに申請方法や具体的な支援内容、注意点を整理し、表や具体例を交えて説明していきます。 情報の深堀を行い、かゆいところにも手が届く内容を目指しているので、今後の生活設計の参考にしてみてくださいね。
本サイトは透析治療に関する情報提供を目的として運営されています。 掲載されている情報の内容を完全に保証するものではありません。
透析治療は患者様一人ひとりの病状や体調により適切な治療法が異なります。本サイトの情報は一般的な参考情報として提供するものであり、個別の治療方針や医学的判断の代替となるものではありません。
透析に関するご不明な点や体調の変化、治療内容については、必ずかかりつけの医師や透析施設の医療スタッフにご相談ください。
本サイトは特定の透析施設や治療機器、医療機関を推奨するものではありません。施設選択や治療方針の決定については、医師との十分な相談のもと患者様ご自身でご判断ください。
透析治療中の食事療法、運動療法、薬物療法に関する情報についても、患者様の病状に応じて制限や注意事項が異なる場合があります。実践される際は事前に医療スタッフにご確認ください。
本サイトの情報は予告なく変更または削除される場合があります。また、システムメンテナンスやその他の事情により、一時的にサイトをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
この記事は、一般的な情報提供を目的としており、個別の病状や治療法に関する医学的なアドバイスを提供するものではありません。透析治療に関する具体的なご相談は、必ず医療機関を受診し、医師の診断と指導に従ってください。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
